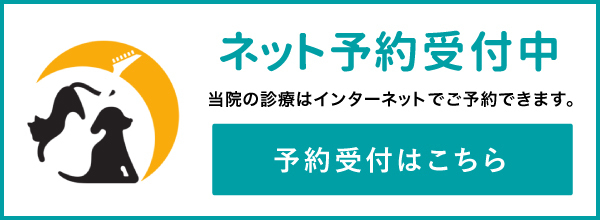犬が水をよく飲むのは糖尿病?|見逃せない症状と治療のポイント
2025年8月

「最近、愛犬がやたらと水を飲むようになった」「おしっこの量が増えた気がする」「なんだか体重が減ってきたかも」
こうした小さな変化に気づいた飼い主様はいらっしゃいませんか?もしかすると、それは糖尿病のサインかもしれません。
犬の糖尿病は、正しい知識と適切な治療、そして日々の丁寧なケアによって、愛犬の健康を長く保つことができる病気です。
ただし、そのためには飼い主様の理解と継続的なサポートがとても大切です。
そこで今回は、犬の糖尿病について、「そもそもどんな病気なのか?」という基礎知識から、治療法、日常生活で気をつけたいポイントを解説します。
犬の糖尿病とは?
糖尿病とは、血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が慢性的に高い状態が続く病気です。
原因の多くは、インスリンというホルモンの分泌不足や、インスリンがうまく作用しないことにあります。
インスリンは、すい臓から分泌されるホルモンで、体内の血糖値を正常に保つ大切な役割を担っています。しかし、インスリンの働きに異常があると、血糖値が高い状態が続き、さまざまな不調が現れてしまうのです。
特に犬の場合は、7歳以上の中高齢での発症が多く見られます。
また、メス犬や避妊手術を受けていない犬では、ややリスクが高いといわれており、しばしば発情後に見られることもあります。
発症には遺伝的な素因に加えて、肥満や感染症、運動不足などの環境的な要因が関わっていると考えられています。
なかでも栄養状態は発症頻度に影響を与えるとされており、肥満を改善することで症状が軽くなるタイプの糖尿病もあります。
そして、糖尿病をそのまま放置してしまうと、白内障や尿路感染症などの合併症を引き起こすことがあります。
さらに進行すると、「糖尿病性ケトアシドーシス」と呼ばれる命に関わる状態に陥る可能性があり、重度の場合には糖尿病性昏睡に至って命を落としてしまうこともあります。
そのため、早い段階で異変に気づき、適切に対応することがとても大切です。
猫とはどう違う?犬の糖尿病の特徴
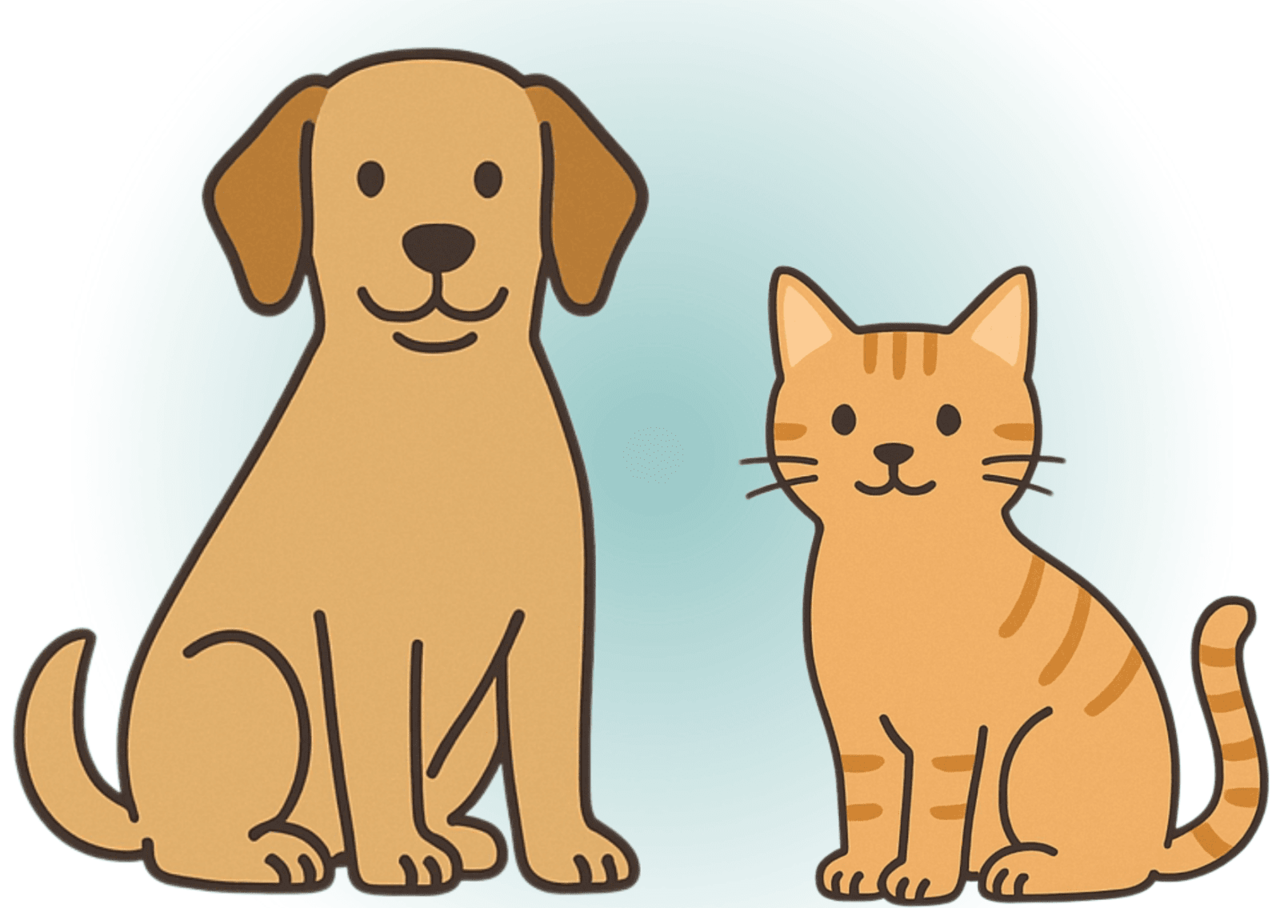
同じ糖尿病でも、犬と猫ではその特徴や治療のゴールに違いがあります。
猫の糖尿病では、インスリン治療と適切な管理によって症状が改善し、治療を休止できる「寛解(かんかい)」という状態に入ることがあります。
しかし犬の場合は、一度糖尿病を発症すると基本的に完治することはなく、生涯にわたる管理が必要となります。
これは、犬の糖尿病の多くがヒトの1型糖尿病に類似しており、膵臓でのインスリンの合成や分泌能力を失っていることが原因です。
一方で、猫ではヒトの2型糖尿病に近いタイプが多いとされています。
そのため、糖尿病を発症した犬には、毎日のインスリン注射とあわせて、食事や運動を含む生活全体の管理を生涯続けていく必要があります。
こうした違いを知ることは、治療に前向きに取り組むうえでとても大切な第一歩です。
愛犬が糖尿病と診断された際には、「病気を治す」ことを目標にするのではなく、病気と上手に付き合いながらできるだけ長く健康に暮らしていくという視点がとても重要になります。
こんな症状が見られたら要注意|糖尿病のサイン
犬の糖尿病は、はじめは少しの変化として現れることが多く、気づかないまま進行してしまうこともあります。
以下のような症状が見られたら、注意が必要です。
- 水をよく飲むようになった(多飲)
- おしっこの量や回数が増えた(多尿)
- 食欲はあるのに(むしろ多食)体重が減ってきた
- 以前より元気がなく、疲れやすくなった
- 目が白く濁ってきた(白内障の兆候)
これらの症状は、糖尿病だけでなく他の病気でも見られることがあります。
しかし、「多飲・多尿」と「体重減少」が同時に見られる場合は、糖尿病のサインである可能性が高いため、特に注意が必要です。
治療の基本は「インスリン注射」と「食事管理」
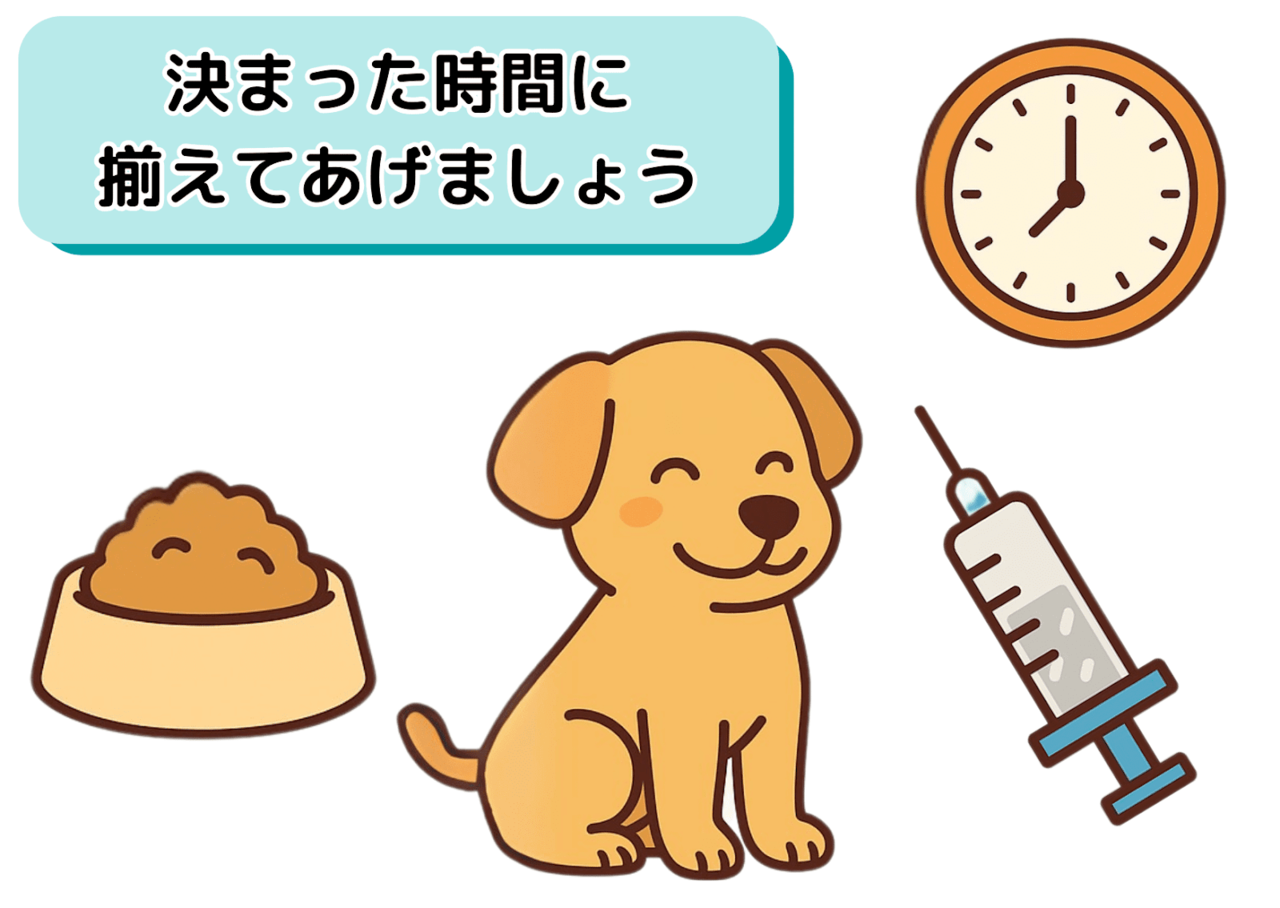
犬の糖尿病治療では、インスリン注射と食事管理の2つが治療の柱となります。
糖尿病は、完治を目指すというよりも、症状を安定させて健康を維持するために「コントロールする」ことが重要な病気です。
<インスリン注射>
糖尿病の犬には、毎日決まった時間にインスリン注射を行うことが基本です。
治療を始めたばかりの頃は、動物病院で打ち方や注意点をしっかり教えてもらいながら、徐々にご自宅での注射を習得していきます。
注射には細い針を使うため、痛みはほとんどなく、慣れてくると飼い主様でも無理なく行えるようになります。
<食事管理>
血糖値を安定させるためには、食事の内容やタイミングの管理もとても重要です。
以下のようなポイントを意識してみましょう。
- 低GIの療法食を選ぶ(血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます)
- 食事の時間と内容、給餌量をなるべく一定にする
- インスリン注射のタイミングと食事の時間をそろえる(血糖のバランスを整えやすくなります)
- おやつや間食は控える(食後の血糖値の乱高下を防ぎます)
こうした日々の工夫と継続的な管理によって、高血糖による体への負担を軽減し、愛犬の生活の質(QOL)をしっかり保つことができます。
<基礎疾患や併発疾患の治療>
糖尿病治療をよりよく進めるために、糖尿病の背景にある基礎疾患(卵巣疾患、副腎疾患など)や併発疾患(炎症性疾患など)を適切に治療することも重要です。
これらの病気を治療することでインスリンに対する反応(インスリン感受性)が改善され、長期的な糖尿病のコントロールがしやすくなることがあります。
生涯にわたるケアと、毎日の管理ポイント
犬の糖尿病は、一時的な治療では改善が期待できない慢性の病気です。
そのため、毎日のインスリン注射と食事管理を継続して行うことが、愛犬の命を守るうえでとても大切になります。
もし治療を中断してしまうと、体内の代謝バランスが崩れ、命に関わる「ケトアシドーシス」という危険な状態に陥ることがあります。
また、慢性的な高血糖が続くと、目(白内障)・腎臓・神経などに徐々にダメージが蓄積されてしまう恐れもあります。
そのため、以下のような日々の継続的な管理がとても重要になります。
- 愛犬の様子や行動の変化に日頃から注意する
- 毎日決まった時間に食事とインスリン注射を行う
- 定期的に血糖値や尿の検査を受ける
- おやつの与え方や運動量にも気を配る
※過度な運動は低血糖のリスクがありますが、軽いお散歩は代謝の維持に役立ちます
<万が一に備えて、低血糖への準備も大切です>
また、低血糖が起きたときの備えとして以下のような点に気をつけましょう。
・ブドウ糖液や砂糖水を常備しておく
・低血糖が疑われるときの対応方法を確認しておく
・緊急時にすぐ連絡できるよう、かかりつけの動物病院の連絡先をわかりやすい場所に控えておく
こうした小さな積み重ねが、糖尿病と向き合う愛犬の健康を守り、健康寿命を延ばす大きな力になります。
まとめ|当院では生涯を見据えた糖尿病管理を行っています
犬の糖尿病は、一生付き合っていく必要のある慢性疾患です。
ですが、適切な治療と飼い主様の愛情あるケアがあれば、快適な生活を送ることができます。
その意味でも「コントロールする」ことが一番の治療であり、予防につながります。
当院では糖尿病と診断されたその日から、インスリン注射の打ち方のご指導、食事内容やライフスタイルに合わせたアドバイス、定期的な血糖値のチェックと健康管理を通して、愛犬と飼い主様を生涯にわたってサポートしてまいります。
小さな異変でも構いませんので、気になることがあればどうぞお気軽にご相談ください。
神奈川県相模原市を中心に大切なご家族の診療を行う
かやま動物病院