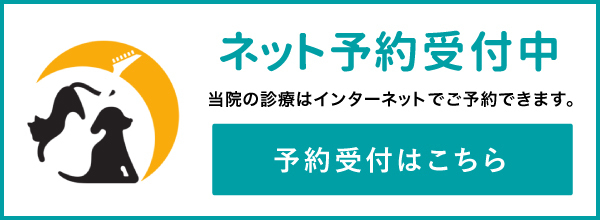猫風邪は完治しない?|ウイルスとの付き合い方と再発を防ぐ暮らしの工夫
2025年7月

猫風邪の原因となるウイルスに一度感染してしまうと、例え症状が治まったとしても、体内からウイルスが完全に排除されることは少なく、多くの場合はそのままウイルスを持ち続けることになります。
そのため、季節の変わり目や体調の変化、ストレスなどのタイミングで、再び症状が現れることもあります。
また、感染の初期段階では症状がとても軽いため、見逃してしまいやすいという特徴もあります。
その結果、飼い主様が異変に気づいたときにはすでに症状が進行しており、重い状態になっていることも少なくありません。
そこで今回は、猫風邪とはどのような病気なのか、どんな症状が見られるのか、そして日常生活の中でどのように早期発見に取り組めるのかを解説します。
猫風邪とは?|ウイルスによる上部気道感染症
「猫風邪」とは、猫に見られる上部気道感染症の総称です。
猫の伝染性上気道疾患(Infectios feline upper respiratory tract disease:FURTD)は若齢猫で最も遭遇する可能性の高い感染性上気道疾患の一つです。
その主な原因はウイルスであり、特に「猫ヘルペスウイルス(FHV-1)」と「猫カリシウイルス(FCV)」の2種類がよく知られています。
これらのウイルスに感染すると、くしゃみや鼻水、目やになど、まるで人の風邪のような症状が見られ、通常は感染してから2〜10日ほどの潜伏期間を経て、徐々にこうした症状が現れてきます。
また、感染力が非常に強いため、多頭飼育をされている環境や外に出る猫では感染のリスクが高くなります。
特に猫ヘルペスウイルスについては、一度感染するとウイルスが体内の神経節などに潜伏し、たとえ症状が治まっても完全に消えることはありません。
そして、体調が崩れたり、ストレスを受けたりしたタイミングでウイルスが再活性化し、再び症状が出てきます。
原因となる猫ヘルペスウイルスと猫カリシウイルスは環境中に蔓延しており、感染させないようにするのは非常に難しいため、完全に治すというよりも、症状が出ない状態を保ちながら上手に付き合っていくことが現実的な目標となります。
見逃さないで!猫風邪のサインとは?

猫風邪は、初期段階ではごく軽い症状しか見られないことが多く、日常生活の中で気づきにくいケースも少なくありません。
見逃しやすい猫風邪のサインをご紹介します。
- くしゃみや鼻水(透明~黄色っぽい鼻汁)
- 目やに、涙目
- まぶたの赤みや腫れ
- 目をしょぼしょぼさせる
- 食欲が落ちる
- 元気がなくなる
- 声がかすれる、鳴かなくなる
これらは猫風邪に見られる典型的な症状ですが、すべてが同時に出るわけではありません。
特に初期段階では、くしゃみが1日に数回出る程度で終わることもあり、「ホコリでも吸ったのかな」と見過ごされることもあります。
FCVでは発熱、元気消失の他に口腔内の潰瘍(口内炎)が主要病変になり、FHV-1では結膜炎や、くしゃみ・鼻水の鼻炎症状を呈することが多いです。
いったん症状が落ち着いたとしても、体調の変化やストレスをきっかけに、再び症状が現れることがあります。
特に以下のようなタイミングは注意が必要です。
- 季節の変わり目(寒暖差が大きくなる時期)
- 引っ越しや模様替えなど、生活環境の変化
- 新しい猫や人との接触
- 他の病気にかかって体力・免疫力が落ちた
- 全身麻酔
- ステロイド等の免疫抑制剤の使用
愛猫の様子に少しでも気になる変化があったときは、早めに動物病院に相談することをおすすめします。
症状が似ていても別の病気かも?|見極めが大切な理由
「鼻水が出ているから、きっと猫風邪だろう」と思っていても、実は以下のような病気が潜んでいることもあります。
- 鼻腔や副鼻腔にできた腫瘍
- 鼻の中に入ってしまった異物(草の種など)
- アレルギー性鼻炎
- 慢性副鼻腔炎
- 歯の根元に起きた感染が原因の鼻水やくしゃみ
このように、症状だけでは猫風邪と見分けがつきにくい病気もあるため、正確な診断がとても重要になります。
猫風邪はうつる?

「猫風邪」という言葉を聞くと、「人間や他の動物にもうつってしまうのでは?」と心配される飼い主様もいらっしゃるかもしれませんが、猫風邪の原因となる猫ヘルペスウイルスや猫カリシウイルスは猫に特有のウイルスであり、人や犬など他の動物に感染することはありません。
ただし、猫同士の間では非常に感染力が強いため注意が必要です。
くしゃみによる飛沫や、鼻水・涙などの分泌物を通じて、簡単にうつってしまうことがあるため、以下のような状況では特に注意が必要です。
- 保護猫や新しく迎えた猫との接触
- 多頭飼育をしているご家庭
- 外に出る猫
また、健康な猫の免疫機能であればこれらの病原体を排除できますが、子猫や高齢猫、持病のある猫、猫免疫不全ウイルス感染症(FIV)や猫白血病ウイルス感染症(FeLV)などに罹患している猫は免疫力が弱っているため、感染を防ぎきれず、症状が悪化しやすい傾向があります。
新生児の場合、母猫が出産や授乳によるストレスを受けることで、体内のウイルスが活性化してしまうことがあります。
その結果、毛づくろいなどのお世話を通じて、母猫の分泌物から感染してしまうケースが多く見られます。
一見軽いくしゃみや鼻水であっても、呼吸が苦しくなったり、食欲が落ちたりと、体への負担が大きくなることがあるため、注意深く観察することが大切です。
予防と再発対策|日常からできるケア
猫風邪のウイルスは体内に残りやすく、再発をくり返すことがあるため、症状が出ない状態を保つことを意識した日常のケアが大切です。
ワクチン接種の重要性
猫風邪の原因となるヘルペスウイルスやカリシウイルスは、混合ワクチンの接種によって重症化を防ぐことができます。
感染を完全に防ぐことはできませんが、症状の軽減や命にかかわる合併症の予防において非常に有効です。
野良猫との接触を避ける・室内飼育の徹底
外に自由に出入りする猫や、庭やベランダで過ごすことの多い猫は、ウイルスを保有している野良猫と接触するリスクがあります。
猫風邪ウイルスは、くしゃみなどの飛沫を介して空気中でも感染する可能性があるため、できる限り室内での生活を基本としましょう。
また、新しく猫を迎える際には、健康状態が安定するまで既存の猫との接触を控えるなど、隔離期間を設けることが重要です。特に幼若猫は重篤になりやすいため、他の猫から隔離する措置も有効です。
免疫力を保つ生活環境を
免疫力が落ちると、体内に潜伏していたウイルスが再活性化し、再発のきっかけになります。
そのため、猫の体調を支える安定した生活環境づくりが、再発防止に効果的です。
・室温・湿度の適切な管理(特に寒暖差を避ける)
・猫が安心して過ごせる静かな空間づくり
・栄養バランスのとれた食事
・定期的な健康チェックとストレスケア
・サプリメントの併用
特に季節の変わり目や引っ越し、家族構成の変化といった環境の変化がある場合には、猫の様子をいつも以上に丁寧に見守ってあげてください。
まとめ
猫風邪は「完全に治る病気」ではなく、上手に付き合っていくことが大切な病気です。
たとえウイルスが体に残っていたとしても、適切なケアと予防によって症状を抑えることはでき、猫が快適に過ごせる時間をしっかりと確保できます。
くり返すくしゃみや鼻水を見過ごしてしまう前に、その背景にあるウイルスの存在を理解し、早めに動物病院に相談することが大切です。
神奈川県相模原市を中心に大切なご家族の診療を行う
かやま動物病院